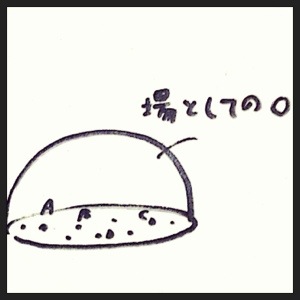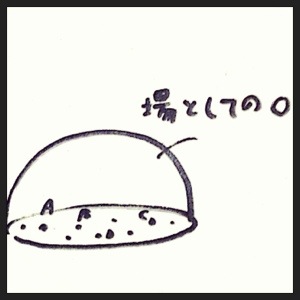歌人、穂村弘の歌論集。2008年に伊藤整文学賞も受賞しています。
様々な媒体に載った歌論を、章立てて構成した物になっていて、一つ一つが短いのでとても読み易い本です。
基本的には、幾つかの短歌を引用して、そこに在る特性や視点、凄味、深み、時代や変遷など多くの視点から解説をしています。
歌人にとって、どう読むかと言う事も重要な仕事の様で、短歌(または歌人の感性)に対して対等、真摯かつ予断を許さず向かい続ける姿勢が、全面よりひしひしと伝わってきます。
興味深いと思ったのは、文中では「酸欠」とも表現する、現在の歌人を覆う状態や、それと連関するリアリティの変遷の説明。
斉藤茂吉など、近代短歌では「生の一回性とその重みを至上とする」が、モードの多様化(命の重さからの自由、言葉や命のモノ化と言うフェティッシュ)では死への実感の喪失が起こる。女性の詠む「僕」などに代表される「私の拡張」は、外部の物語や目的の喪失により、命の使いどころが無くなった事による。そこで、命はそれ自体が目的化して何処までも肥大化する。
また「誰もが心のどこかで、これは普通ではない、という気持ちを抱きながら普通に生きている」実感が、近年の歌では詠われている。とも指摘しています。「かけがえの無い<われ>が、言葉によってどんなに折り畳まれ、引き延ばされ、切断され、乱反射され、時には消去されているようにみえても―略―生の一回性と交換不可能性のモチーフは必ず「かたちを」変えて定型内部に存在する。」
など、短歌の詠ってきた命のスケールの大きさや広がりを強く実感する事が出来ました。
時代や社会の要求する大きな目的の喪失。身近で極個人的なモチーフを追及する傾向は、短歌や文学に限らず、あらゆるものづくりや表現にも繋がる問題であるとも思います。
クラフトと工芸の違いと言う所も、根源的にはそう言う所にあると思います。
「人類史上もっとも幸福で、しかし心のレベルとしては最低の生を生き、種の最期に立ち会おうとしている我々」ともありましたが、そう言った現実を真っ直ぐに見つめ、描き続ける歌人と言う仕事には、感服するばかりでした。